㈱オフィスクアトロは大阪府守口市に本社を置いている。
守口市は淀川の左岸にあって、大阪市の北東に隣接する人口約14万人の
小さな都市である。大阪市の北東部ではあるが大阪府から見れば大阪府の
ほぼ中央に位置している。
守口の名前の由来は秀吉時代の「守り口」ではないかという説があるが
元々は飯盛山の原生林への入り口の「森口」であったのが石山本願寺や
大阪城の軍事的な意味で「守口」に変型したとの説が有力である。
守口の名前は室町時代の来迎寺縁起(1372年)に既に登場している。
織田信長、池田信輝の統治を経て大坂夏の陣で豊臣家が滅びるまでは
豊臣家の直轄領であった。
全国的には守口は三洋電機の本社の所在地や隣の門真市の
PANASONIC (松下電器) として知られているのかも知れない。
守口市松下町には松下電池工業もある。
この小さな守口には意外と歴史があり、東海道五十三次は江戸から
京都までの道筋であったが江戸時代に入ると大坂までの4つの宿場町を
加えて、東海道五十七次と称せられた。
守口は大坂からの最初の宿場町となり、江戸日本橋から来ると最後の
宿場町である。
宿場町としての守口には大名が宿泊する本陣も置かれて栄えたとの
ことである。
本編では守口の歴史と散策の一端を紹介しよう。
守口に本社を置く㈱オフィスクアトロと守口との関係も深いものであり、
何故ここであえて守口を紹介するのかはいずれ読者の知るところとなる
はずである。
㈱オフィスクアトロが守口にあるのは意味がある。
次に紹介する「守口」は、いずれも守口に長く在住する者のみが知る裏話や
秘話も含めて紹介している。
 守口市旗
守口市旗
 守口市
クリックで拡大
守口市
クリックで拡大
 守口市役所
クリックで拡大
守口市役所
クリックで拡大
交通の要所
守口は近年は大阪市電や大阪市営バスの終点として発達してきたがさらに京阪電車の京橋駅から
最初の急行の停車駅でもあり、京阪百貨店や守口プリンス・ホテルを前身とする
守口ロイヤルパインズホテルや地下鉄谷町線の終点駅でもあった(現在では大日が終点) 。
道路では阪神高速守口線の終着でもあり、中央環状線と国道一号線との交差点でもある。
また伊丹空港へのモノレールの大日駅も擁している。
このように交通の要所のひとつでありながら最近では大日や守口駅周辺にも高層マンションが
建つようになってきた。自動車や地下鉄、京阪電車、そして伊丹空港や新幹線にもアクセスが容易である。
三洋電機
三洋電機の発祥は守口市本町であり自転車用の発電ランプを最初に
作ったのが始まりとされている。
その後、ラジオや洗濯機、テレビを発売した。
創業者は淡路島出身の 井植 敏男 は松下幸之助のもとで電気ソケットを
作り三洋電機本社とともにすぐ近くには井植氏邸宅がある。
( 井植氏邸宅の隣りのタバコ屋も井植家の縁戚のようである。)
井植氏は一度、松下電器を退職して故郷の淡路島に戻ってしまうが
彼の商才を惜しんだ当時の住友銀行の支店長が井植氏を説得して大阪に
連れ戻すのである。
井植氏の故郷・淡路島との関係は深く淡路フェリーは井植一族による
経営であり三洋電機は積極的に淡路島の企業に外注を行うようになった。
三洋電機はまた松下電器とは経営者どうしで親交が深く近所の
松下記念病院も PANASONIC と三洋電機社員との共同利用である。
現在では三洋電機は業務用の冷蔵庫や自動販売機に高いシェアを
誇っているが業務用の部品のサプライに強く、何と IBM S/34 の
モーターには三洋電機製が使われていたのである。
「三洋村」とも揶揄される守口には三洋電機所有の土地不動産が多く、
最近ではマンション建築販売にも積極的に乗り出してきている。
三洋電機の元役員宅にマンションを初めて建設してから今では
京阪守口市駅前にも高層マンションを建設して販売するまでに至っている。
 三洋電機本社ビル
クリックで拡大
三洋電機本社ビル
クリックで拡大
 井植邸宅
クリックで拡大
井植邸宅
クリックで拡大
一里塚
東海道五十七次の目印としての守口の一里塚も残っている。
ただし目立たない奥まったところにあるので探すのに苦労する。
一号線から左のわき道へ入ってしばらく行くと一里塚が左手に見えてくる。
一里塚は驚くほど背の低い小さな石であり、このことからも当時は
周りには大きな建物は無かったものと思われる。
この写真の石碑は一里塚ではなく一里塚の跡を示す守口教育委員会による碑である。
 一里塚の跡を示す碑
クリックで拡大
一里塚の跡を示す碑
クリックで拡大
大塩平八郎ゆかりの書院
守口の一号線に面して非常に特徴のある旧い邸宅が残されている。
これは大塩平八郎ゆかりの書院跡と呼ばれている。
江戸時代の天保に大坂町奉行所の与力であった大塩平八郎が
米不足やワイロ政治に反発して一揆を企て大阪城の占拠を計画。
親子を中心として武装蜂起したのが世に言うところの
「大塩平八郎の乱」である。
挙兵は簡単に失敗に終わったものの島原の乱以降 200年ぶりの
合戦として江戸幕府の失政に一石を投じるものであったと言われている。
この乱を密談して計画したのではないかと言われているのがこの書院跡である。
現在は白井家の個人宅になっているが大塩平八郎を後援していた
豪農白井孝右衛門の邸宅として今も残されている。
白井家には大塩平八郎が使ったという書院が残されており (非公開)ここで
「大塩平八郎の乱」の相談がなされたのではないかとの歴史がある。
この書院跡は国道一号線に面していて㈱オフィスクアトロからもすぐ
近い場所にある。
 大塩平八郎ゆかりの書院
クリックで拡大
大塩平八郎ゆかりの書院
クリックで拡大
守口大根
愛知県の名産として知られる守口大根は、守口が発祥である。
守口大根は 1 メートル以上はある細長い大根であり、
守口が砂地であったことからこのような大根が育ったのではないかと
推測される。
秀吉が守口に立ち寄ってこの大根を食して美味であると褒めて
守口大根と命名されたと言われている。
残念ながら現在では守口大根はその名を愛知県に譲っている。
 守口漬
クリックで拡大
守口漬
クリックで拡大
 守口大根
クリックで拡大
守口大根
クリックで拡大
江戸川乱歩
「名探偵明智小五郎」で知られる、江戸川乱歩が最初にミステリー小説を
書いたのが守口の大野産婦人科の2階の下宿であり㈱オフィスクアトロの
わずか数十メートルのところにある。
これは残念ながらつい最近になって取り壊された。
この乱歩の寓居の跡とされる場所は偶然にも豊臣時代の淀川の流れる
位置でもあった。
つまり㈱オフィスクアトロは豊臣期の淀川河川敷に位置していると言える。
 江戸川乱歩居住跡
クリックで拡大
江戸川乱歩居住跡
クリックで拡大
大阪遷都
鳥羽伏見の戦いで徳川幕府軍に勝利した大久保利通は大阪遷都の案を
明治天皇に奏上した。
しかし岩倉具視をはじめとする公家たちの猛烈な反対にあったために、
天皇に大坂を案内するという名目で大阪へ天皇を案内した。
このとき天皇が宿泊したのが守口の難宗寺である。
大阪城へ敗走した幕府軍を追うように守口まで来たのである。
激しい雨中の中、明治天皇は三種の神器を携えて夜9時ごろに難宗寺に
到着して一夜の宿を取り、守口が一夜だけの都となったということである。
( 実は明治天皇はこのあくる日には大阪市旭区太子橋(旧・橋寺町) に
訓練の視察に訪れていたことが石碑によって残されている。)
しかし大坂が都になるという計画は江戸無血開城によって幻となった。
つまり明治天皇の本拠地はそのときはまだ京都にあり、正式には
東京遷都で初めて東京に移るのである。
大久保利通は江戸は炎上するものと予測して大坂を代わりの首都として
考えたのだろう。
しかし江戸城の無血開城は大久保にも予測できなかったようである。
このため大坂遷都は幻のものとして終わった。
 難宗寺
クリックで拡大
難宗寺
クリックで拡大
明智光秀による守口城
意外と知られていないのが守口城である。
最初に守口城が築かれたのは室町時代の後期とされているが象徴的であるのが明智光秀による
守口城または砦の築城である。
明智光秀は織田信長の命によって蓮如の石山本願寺を攻めたときに築城したのが
守口城であると言われている。
また守口城は難宗寺が本丸の跡であると言われたり、現在の土居あたりにあったのではないかとの説もある。
[註] 「土居」とは軍事用の目的のための土塁を意味している。
光秀は蓮如の留守中に、今すぐ攻めれば本願寺は落ちると確信したが信長の命によって
やむなく自らが攻撃することなく陣を退いた。信長と光秀の微妙な駆け引きが感じられる。
大坂夏の陣
大坂夏の陣で豊臣家は滅びることになるが、淀君の侍女として使えた
「おきく」の「おきく物語」でおきくが大阪城から逃れて落ち延びたのが
守口であるとされている。
「おきく物語」は徳川幕府の政権下になって出版された物語である。
大坂夏の陣では大阪城だけが炎上したと思われているが実は大阪の
ありとあらゆる場所が猛火に包まれて大阪中の一般市民を巻き込む
大パニックであったようである。
逃げ惑う大阪の人々の様子が大阪城の天守閣に展示されている。
 おきく物語
おきく物語
 大坂夏の陣
クリックで拡大
大坂夏の陣
クリックで拡大
旭区太子橋にある御野立所と五箇樋跡
守口市を歩いていると「時空の旅」という守口市教育委員会による
現代の道標に気づく人も少なくはないだろう。
この中でいくつか「五箇樋跡」を示す道標があるが、いくら探しても
見つからないのではないだろうか ?
守口市マップや歴史散策を紹介しているウェブ・サイトでも
「五箇樋跡」を明確に紹介しているサイトはほとんどない。
この謎を明らかにするために、あえてここで五箇樋跡を紹介する。
これは実は大阪市旭区の淀川沿いに存在しているので守口市を
探したのでは見つからない。
「五箇樋跡」とは五ケ庄(守口庄、小瀬庄,橋波庄、寺方庄、稗島庄) への
淀川からの飲料水を引いていた跡のことを意味する。
現代では近くに庭窪浄水場があるのは興味深い。
「五箇樋跡」は大阪市旭区太子橋の淀川の堤防の縁に
「御野立所」とともに残っている。
「御野立所」とは大正天皇が明治43年にこの地で工兵隊の架橋訓練を
視察された記念を残している碑である。
 五箇樋跡
五箇樋跡
 御野立所
御野立所
緑道公園
元、運河の跡であるが緑と桜並木として整備された緑道公園は
㈱オフィスクアトロへ至る散策の小道でもある。
この都会にあってもわずかに残された緑に包まれた小道は
オアシスでもあり、あるときは哲学的な雰囲気も与えてくれる。
春には桜並木が美しく迎えてくれる。
緑道公園の西側に広がる松町、竹町、桃町は守口市の高級住宅街と
知られておりゆったりとした一戸建て住宅街が広がっている。
 緑道公園
クリックで拡大
緑道公園
クリックで拡大
守口宿
「守口宿」と「文禄堤」という名前の日本酒がある。
日本酒「文禄堤」のボトルのラベルを飾っているのは文禄堤にかかる
「本町橋」である。
このラベル絵は守口市の名誉市民である画伯によって描かれたとの
解説がボトルの裏面に書かれている。
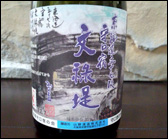 特吟純米酒「文禄堤」
クリックで拡大
特吟純米酒「文禄堤」
クリックで拡大
ふる里守口を訪ねて
守口を詳しく解説した書籍として
駒井正三著「ふる里守口を訪ねて」(守口市発行) がある。
著者・駒井正三氏は故人であるが㈱オフィスクアトロ代表取締役池田一明の池田家とは家族ぐるみの付き合いの長い親しい関係にある人である。
また駒井氏は立命館大学史学科を卒業され、長年、教職にあり守口の
郷土史の編纂にも携わっていたとのことである。
守口の歴史をこれほど詳しく紹介している本は他に例を見ない。
「ふる里守口を訪ねて」は守口市役所で入手することができる。
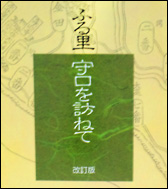 ふる里守口を訪ねて
クリックで拡大
ふる里守口を訪ねて
クリックで拡大
守口の続きは ...
守口をいろいろと紹介してきたが実は守口を最も象徴するものを敢えて紹介していない。
それは今後の㈱オフィスクアトロと密接に関係が深くなるので改めたて詳しく紹介したいと考えている。
